今年、衛生管理者の資格を取得した奥野が、働く職場で役に立ちそうな知識を皆様にお伝えします。仕事に興味を持つというよりかは、職場での自分の身の振り方を考える機会の参考になれば幸いです。
衛生管理者とは?
衛生管理者は、50人以上の従業員が働く事業所に必ずいなくてはならいと法律で定められている国家資格です。もう少し詳しく説明すると、労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者のことを指します。
国家資格と言われると難易度が高そうと思われるかもしれませんが、他の資格と比べるとそこまで難しくはありません。衛生管理者には第一種と第二種があり、それぞれの合格率は約45%と約53%(ユーキャンより抜粋)と合格率が1割もない他の国家資格(弁護士、医師等)よりはるかに取りやすい資格と言っても過言ではないでしょう。実際、参考書と問題集を用意するだけで取れました。
第一種と第二種の違いですが、第一種は全ての業種で適用することができ、第二種は一部の業種を除いて適用することができます。その為、難易度は第一種の方が難しくなります。第二種で適用外とされているのは、有害業務が含まれる業種(鉱業、医療業等)です。私は有害業務が含まれる業種への転職を考えていなかったので第二種を選択しましたが、もし資格を取ろうと考えている方がいらっしゃいましたら第一種をオススメします。少し難易度が上がる程度なので、どなたでも取れる可能性は十分にあります。それだけでなく、すべての業種に適用できるので、面接や履歴書でもかなり効力があると思われます。
ここからはあくまで個人的な感想ですが、その気になれば参考書と問題集で取得できるので、通信講座や講座の受講等はあまりオススメできないです。衛生管理者で学ぶのは、法律と職場についてのこと、そして体の構造やAEDを用いた救助活動等です。その中でも、体の構造については高校生までに一度学習している内容になります。肝臓の働きや内臓の名称、心臓からの血液の運搬、ホルモンについて等、今までに何度か聞いたことのあるフレーズばかりです。なので、復習感覚で勉強をすることができます。その為、わざわざ高いお金を使って、一度勉強した範囲を講座で受講するのはいかがなものかと、私は思っています。ただ、その方がやる気が出るとか、講座でないと勉強が続かないと言われる方々もいらっしゃいますので、一概に間違っているとは言えません。自分の身にあった勉強ができれば一番です。
知っておいて損はない仕事の知識
残業はしてはいけない

働いた人なら誰でも経験するであろう残業ですが、法律上では原則許されていないことはご存じでしょうか。法律には法定労働時間や所定労働時間で働くことのできる時間の上限を定めています。その為、上限を超えると違反行為となってしまいます。しかし、それでは繁忙期等に対応することができなくなります。
そこで、「36協定」というものが活躍することになります。これは、労働基準法第36条に定められた労使協定のことです。要約すると、会社と労働者の間でこの協定を締結しないと、残業が許されないということです。協定の締結に関わることができる労働者は、労働組合か労働者の過半数を代表するものと定められています。その為、労働者の同意がなければ締結することはできません。
36協定では、時間外労働(残業)の上限も定められており、これを超えてしまうと会社側が罰則を科せられる可能性があります。なので、残業時間があまりにも多いと感じている方は、一度事業所の36協定を確認することをオススメします。もし、36協定が締結されていない、時間外労働の上限を超えている等の問題があった場合は、協定の書面と残業時間を記録した書面を持って、お近くの労働基準監督署に報告しましょう。問題があると判断された場合は、会社に指導勧告や立ち入り調査が行われることになるので、労働環境が少しは良くなると思います。ならなければもう一度報告して、転職しましょう。
有休の日付は会社側が変更することができる

有休は、従業員に与えられた権利であり、取得を妨害することは法律によって禁止されています。しかし、有休を取りたい日付を会社側に変更されてしまうことがあります。これを、時季変更権といいます。
時季変更権とは、会社が従業員の希望した年次有給休暇請求日を一定の条件下で、変更できる権利のことです。これだけ聞くと、我々社会人にとってはまったくメリットのない情報に聞こえてしまいますが、今回お伝えしたいのはそういう話ではありません。
この権利は、業務に支障が出るほどの理由が無ければ行使することはできません。例えば、有給取得者の代替人員を確保できない場合や繁忙期に有休が複数人重なった場合、仕事を多く掛け持ちしている人が長期の休暇を相談もなく一方的に申請してきた場合等が該当します。しかし、「繁忙期」や「人員不足」といった理由だけでは行使することができません。そして何より、この権利には強制力がありません。会社側は明確に内容を示し、かつ、有休取得者にお願いして初めて使用することができます。なので、時季変更権があるから有休を認めない、明確な内容もないのに勝手に日付を変更されるといった場合は、法律に違反しているのですぐに労基等に報告しましょう。
さらに、時季変更権は抽象的な内容の為、下手に行使すると会社側が訴えられる可能性もあるというデメリットがあります。その為、理解している会社であれば、よっぽどのことがない限り行使することはありません。逆に、時季変更権をよく言葉にし、有給取得の抑止力をかける会社は理解していない可能性が高いです。もし、そんな会社で働いている場合は、訴えるのも良し、労基に相談するのも良し、転職するのも良しです。
職場での休憩は、法律によって定められている

それぞれの職場によって、様々な休憩の取り方があると思いますが、そんな休憩の時間や取り方等が法律によって定めれています。例えば、6時間を超える労働には最低でも45分の休憩時間が必要なり、8時間を超えると最低でも1時間の休憩が必要になります。そして、6時間以下の場合は、休憩時間は必要ないとされています(※ただし、必要ないとされているだけで、職場によっては取らせているところもあり、法律的には特に問題はありません)。
上記の内容以外に、「休憩の三原則」といものがあります。
1.一斉付与の原則 = 休憩は一斉にとらせる
2.自由利用の原則 = 休憩中は自由にすごさせなければならない
3.途中付与の原則 = 休憩は労働時間の途中に与えなけれなならない
1は、昼休憩で一斉にランチに向かう従業員をイメージしてもらえればわかりやすいと思います。ただ、業種によってはそれを行うことが難しいこともあり、一部の業種(商業、通信業等)は適用外とされています。個々で休憩をとる職業がこれにあたります。
2は、言葉の通り、従業員には自由に休憩させなければならないという原則です。例えば、休憩時間の終了5分前にはデスクに戻るなど指示を出してしまうと、法律に違反したことになります。なので、企業側が休憩中の従業員に干渉することは違反になると覚えてください。
3は、就業前や就業終了後に休憩をとらせるなという原則です。休憩はあくまで就業中に取らせなければなりません。
この原則すべてを順守することで、「1時間ごとに10分の休憩」や「1日2回に分けて休憩」等の休憩の取り方が認められるようになります。サービス業でよく見かけるパターンです。
ここまでの内容を見ていただいて、今一度自分の職場と照らし合わせてみてください。原則は守られているでしょうか。休憩時間は従業員に取らせなければならいものと定められているものです。少しでもおかしいと思うところがあるのなら、職場に相談してみてください。
まとめ
今回は衛生管理者である奥野から、仕事にまつわる知っておいて損はない知識をお伝えさせていただきました。
・残業はそもそも認めらておらず、会社と労働者たちとの間で36協定を締結することで認められる。
・時季変更権を行使すれば、会社側が有給取得者の有休の日付を変更することができるが、あいまいな理由では変更できず、下手に行使すると訴えられる可能性もある。
・職場での休憩は法律によって定められており、基盤になる「休憩の三原則」というものが存在する。
衛生管理者についても少し触れましたが、資格取得はそこまでの難易度はないのでオススメです。ちなみに、上記の「残業が認められていない」という内容は、よく試験で出題される内容なので、覚えておいて損はないです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
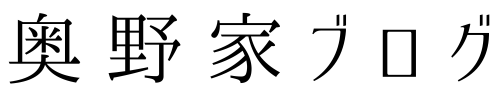
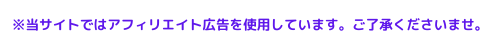



コメント